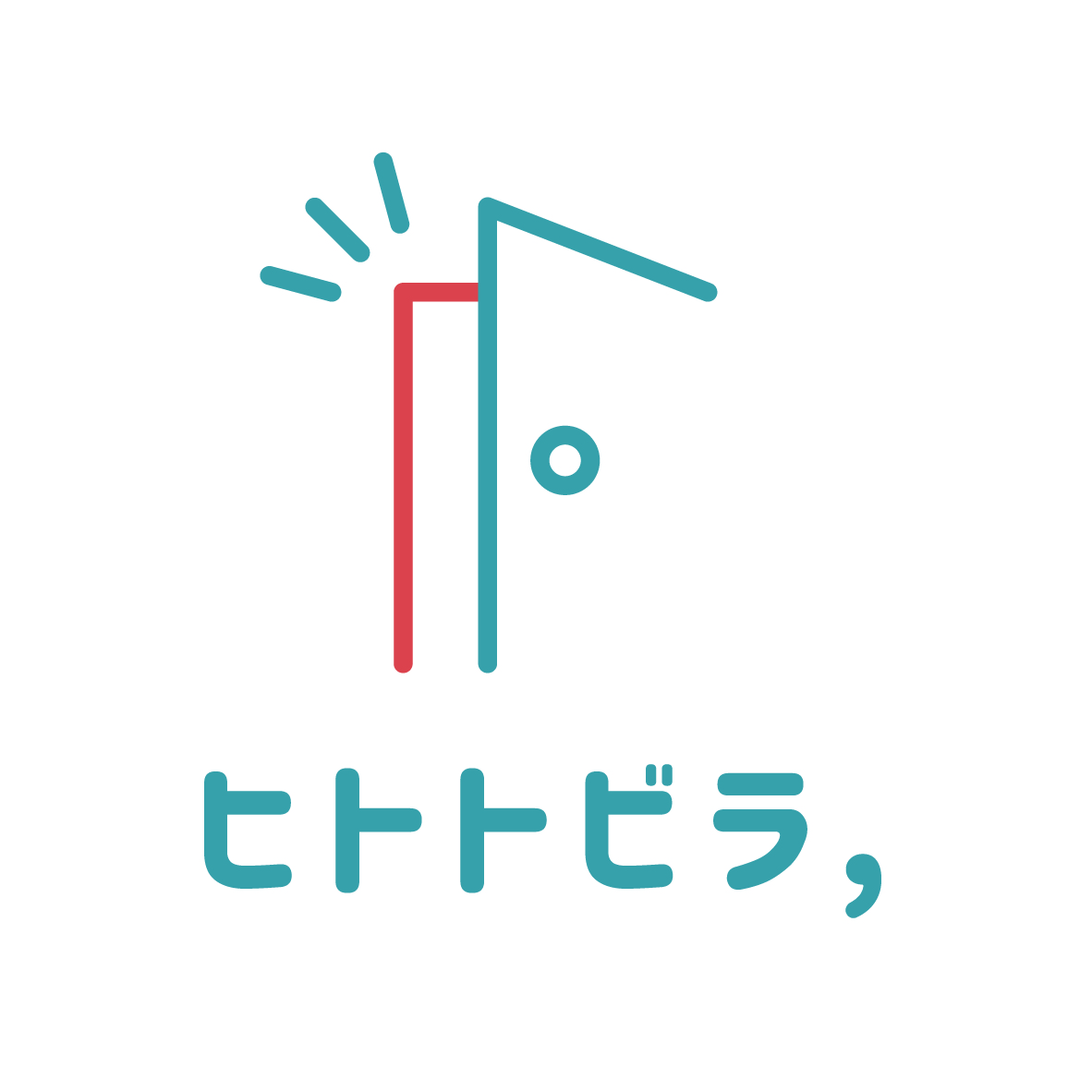「英語だけはもっと早くからやっておけばよかった…」
これは中3や高校生になってから、多くの生徒が口にする“リアルな後悔”です。
なぜ、英語だけがそう言われるのか?英会話との違い、中3の定期テストの変化、そして今の教科書が抱える問題点など、塾の現場で見えてきた“早めの対策”の必要性をお伝えします。
■ 英語は“積み重ね型”——わからないまま進むと迷子になる
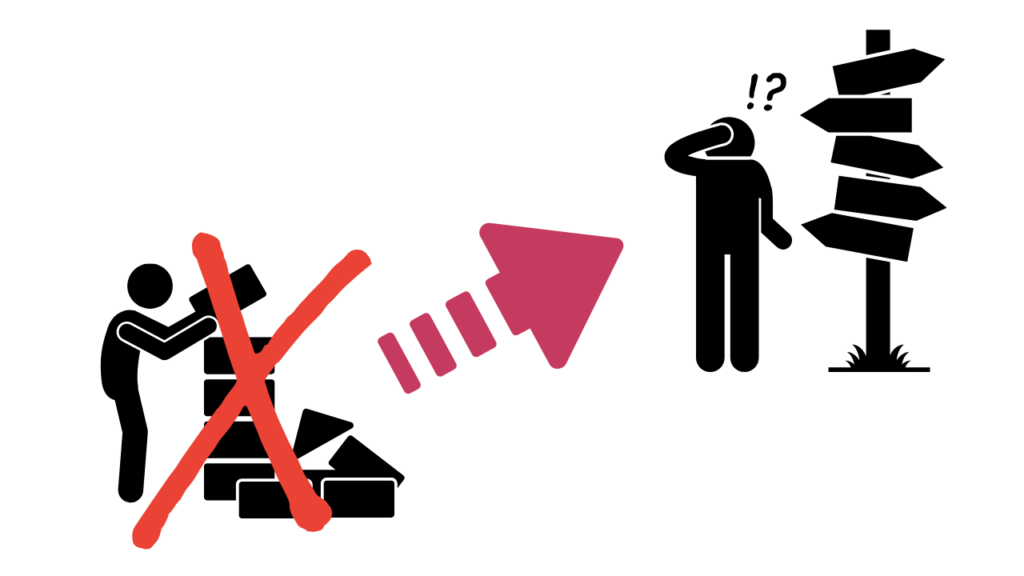
英語は他の教科と比べて、「積み重ね」の要素が非常に強い教科です。
be動詞、一般動詞、助動詞、時制、関係代名詞……
すべてが“前の単元が理解できていること”を前提に進みます。
たとえば「be動詞と一般動詞の違いが曖昧なまま」、「疑問文の語順がよくわからない」という状態のまま学年が進むと、長文読解でも文法問題でも“何となく読む”しかできなくなってしまうのです。
■ 実は…今の教科書が、生徒の混乱を招いているかもしれません

現行の中学1年生の教科書(※多くの検定教科書)では、Lesson1の段階で「be動詞」、「一般動詞」、「助動詞」、「疑問詞」など複数の文法項目が一気に登場します。しかも、文法の体系的な説明は少なめで、会話や場面重視の構成。
つまり、「感覚的に英語に触れる」ことはできても、
• 文法ルールが整理されない
• 文の構造が理解しづらい
• 自分で文をつくれない
といった状態に陥る生徒が出てきます。
これは、文法を土台から理解する“補助学習”をしなければ、いくら教科書を読み進めても定着しないということです。
だからこそ、学校に任せきりにせず、自分のペースで整理し直す機会を持つことが大切です。
■ 英会話をしている=英語ができる、ではない

「うちは英会話スクールに通っているから英語は安心!」
…そう思っている方も少なくありません。もちろん、英会話で「聞く」、「話す」力を鍛えるのは素晴らしいことです。
しかし、入試や学校の定期テストで問われるのは「読む・書く・文法・語彙」の力。
実際、英会話は得意でも、
• 長文が読めない
• 文法問題が解けない
• 英作文が書けない
というケースは珍しくありません。
英語の4技能(読む・書く・聞く・話す)はそれぞれ別の訓練が必要。
英会話をしている生徒ほど、文法や単語の学習とバランスを取ることが重要なのです。
■ 中3の定期テストから“初見の英文”が出てくる
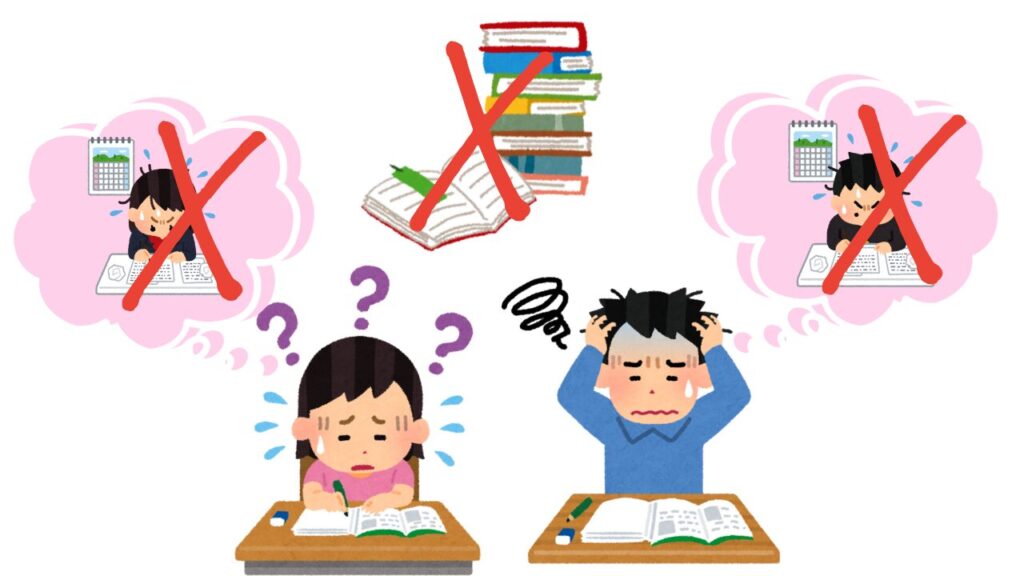
中1・中2の頃は「ワークからそっくりそのまま出た!」ということも多い定期テスト。
ですが、中3になるとそうはいきません。
• はじめて見る英文の読解
• 応用的な文法の使いこなし
• 過去の単元をまたいだ出題
…など、“思考力”や“読解力”が求められる問題が増えていきます。
これは、入試を見据えて「暗記だけでは解けない力」を求められてくるからです。
つまり、表面的な学習では太刀打ちできなくなるのが中3の英語。
この段階で“苦手”があると、そのまま入試につながってしまうのです。
■ 英語は「1日10分」で差がつく教科

とはいえ、いきなり毎日1時間も英語を勉強する必要はありません。
英語は、“短時間×毎日”の積み重ねが効く教科です。
たとえば、
• 毎日英単語10個をチェック
• 教科書の英文を音読する
• スマホアプリで文法のミニテストを解く
など、「1日10分」の習慣で、半年後には驚くほど差がつきます。
早めに取り組むことで、英語が“得意科目”に変わっていくのです。
■まとめ: 「英語だけは早めに」始めた人が、最後に笑う
英語は、つまずくと取り戻すのが難しくなる一方、早めに土台を固めれば中学・高校・入試までずっと有利に進められる教科です。
今は「まだなんとかなる」と思っていても、あとから「もっと早くやっておけば…」と後悔する声は本当に多いです。
逆に、「早めに始めておいてよかった」と言える生徒も、確かに存在します。
だからこそ、英語だけは早めに。
未来の自分が「ありがとう」と言ってくれる一歩を、今から踏み出してみませんか?
次の記事では、実際に英語の成績があがった宜野湾市の生徒のケースを事例に明光義塾で取り組んだことをお伝えします!